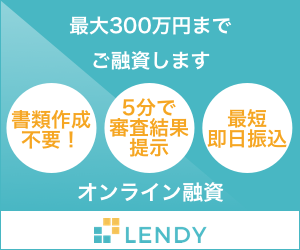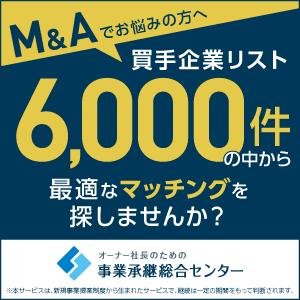年末なので個人事業主の節税策をご紹介します。
節税策としては定番の小規模企業共済ですが、年内に手続きが完了すれば節税可能な内容です(まだギリギリ間に合います)。
また、実際に私も加入しており経験談として記事を書けますので、参考にして頂ければと思います。
1、小規模企業共済とは?
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」で、掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です(独立行政法人 中小企業基盤整備機構のホームページより引用)。
簡単に説明すると、退職金です。
そして節税メリットが大きいです。
個人事業主で節税を考える場合には、優先的に対応すべき内容と考えてもよろしいかと思います。
2、加入のメリットは?
①掛金の支払い時には全額が所得控除される。加入後の増減も可能
小規模企業共済の月々の掛金は、確定申告の際に、その全額を課税対象所得から控除することができるので、節税効果がとても高いです。
また、掛金は、1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額することが可能です。例えば、現時点で今年の所得の見込みが立っているとします。売上が伸びて経費が少なく済んだことから所得が100万円を大幅に超えているとします。この場合、小規模企業共済を月7万円、年額で84万円支払うことで84万円に対応する税額分だけ節税が可能になります。
②共済金の受け取り時にも税制メリットがある。
小規模企業共済の共済金は、退職・廃業時に受け取りが可能です。満期や満額はありません。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなります。
実際には共済金の受け取りのケースにより更に細かい所得の分類がされますが、いずれの場合でも事業所得として課税されるよりも、税率が低くなるため、税制メリットがあるといえます。
②その他
小規模企業共済に加入すると、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することができるようになります。低金利で、即日貸付けも可能です。
3、加入できる人や条件は?
次のいずれかに該当する場合には、小規模企業共済に加入することが可能です。
1、建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2、商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3、事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4、常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5、常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6、上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
なお、「会社等の役員」とは、株式会社・有限会社の取締役または監査役の方、合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員の方を指します(ただし外国法人の役員は除く)。小規模の事業者であれば、個人事業主、法人を問わず幅広く適用される制度だと思います。
細かい加入条件については、公式ホームページでご確認下さい。
4、加入の手続き時の留意点は?
加入の手続きは、必要書類を入手して窓口で記入して提出するだけです。
加入窓口の詳細は、公式ホームページでご確認頂ければと思いますが、自宅の近くの銀行や信用金庫に行って「小規模企業共済に加入をしたい」と伝えれば書類を出してくれます。
加入窓口に行く前に準備しておく必要があるのは、個人事業主の場合には確定申告の控え、法人の役員の場合には、履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)です。
ここで注意したいのは、開業したばかりの個人事業主で確定申告の提出がない場合には開業届の控えを準備すること。確定申告の控え、開業届出の控えのいずれも税務署の受付印があるものであること。
法人の履歴事項全部証明書の場合には、交付後3カ月以内のものであるという条件がある点です。
その他、加入窓口に提出する必要書類の記載内容には特に難しいものはなく、加入窓口の担当者に聞きながら記載すれば問題なく提出できると思います。
ただし、小規模企業共済に新規で加入する場合には1点注意点があります。
小規模企業共済の支払いによる節税効果が得られるのは、その年に支払いをした金額となります。
そのため、上記の例でいうと12月に1月分の7万円しか支払いをしなかった場合には7万円分に対応する効果しか得られません。12月に12カ月分の84万円の支払いをする必要がある点に注意が必要です。
この内容を踏まえて窓口の担当者に相談しながら申込書に記載をすると良いと思います。