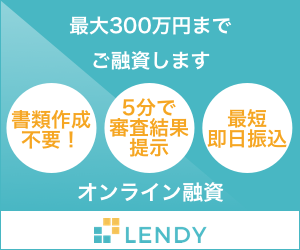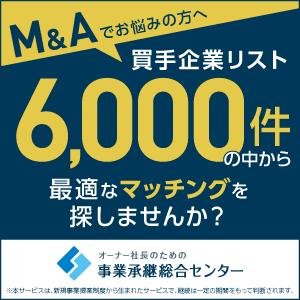創業段階で必要な資金を調達する方法をまとめました。
目次
1.出資
1.1 自己資本
自己資本。創業前に創業のために貯蓄してきたお金のことです。後述する借入金と異なり返済する必要がありませんし、利息の支払いもありません。
自己資本の金額は、金融機関から借入をする時の重要なポイントの一つになります。創業に向けてどれだけコツコツと準備をしてきたかの証拠になるからです。
なお、自己資本の中で、会社設立時に会社のお金として入れるものを会計上では、資本金として取り扱うことになります。
1.2 ベンチャーキャピタルからの出資
いわゆるVCからのお金を入れてもらう方法です。将来的に上場を目指すような成長性の高い事業を予定している場合には、ベンチャーキャピタルからの投資を受けることも選択肢になります。上場を目指す時には事業提携のアドバイスや経営支援を行ってくれるメリットがあります。
ただし、ベンチャーキャピタルに事業計画のプレゼンテーションを行い、今までにない新しい事業モデルで、事業の拡大が見込まれると判断される必要があり、ハードルは低くありません。また、株式を保有されることになりますので、自由に経営をできないという制約も生じえます。創業当初は一人で事業を行い、数名の従業員の採用を将来的に予定している事業の場合にはまずは、別の資金調達方法でスタートするのが良いでしょう。
1.3 エンジェル投資家からの出資
エンジェル投資家はお金をもっている個人の投資家と考えて頂ければよいと思います。このような、エンジェル投資家から出資を受けるという方法もあります。
創業段階で事業内容に関心を持ってくれて投資を受けたというケースや資金繰りが厳しくなった時でも将来を期待されて出資を受けたというケースを見てきています。創業者の知人でエンジェル投資家がいる場合には、出資を受けることを打診するのことも選択肢とは良いと思います。
ただし、ベンチャーキャピタルからの出資と同様に、会社にとっては、株式を保有される事になりますから、経営の支配権について注意して出資を受けるかを検討する必要があります。
事業会社から出資を受ける場合にも同様に注意する必要があります。
2.融資
2.1 親、知人からの借入
融資とは、会社から見ると借入金のことです。通常は、金銭賃貸借契約書を締結し、出資と異なり契約書の条件に従って返済をしていく必要があります。利息の支払いも必要になります。
まずは、親や知人から創業時のお金を借り入るケースがあります。金融機関からの借入金と比較すると緩やかな条件設定をできる点ができる点は良いでしょう。また、知人からの借入金よりも親からの借入金の方が返済条件が緩やかになる(場合によっては返さなくても良い)という点から日本政策金融公庫からの融資を受ける時には評価が高くなるものと考えられます。
2.2 政府系金融機関からの借入 おすすめ
政府系金融機関とは、日本政策金融公庫のことです。日本政策金融公庫は、100%政府が出資している株式会社であり、民間の金融機関の補完をすることを基本理念としています。そのため、創業者を支援するための融資制度が充実しており、創業時の資金調達を考える上ではおすすめの金融機関です。
日本政策金融公庫の融資制度の中には、新創業融資制度という制度があり、これから創業をする方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業に必要なお金の10分の1以上の自己資金を準備することで、最大で3,000万円(運転資金1,500万円)の借入を無担保、無保証で受けることができます。
通常の金融機関の借入の場合には自己資金の準備が創業資金の1/2以上であったり、創業者が連帯保証人になる必要があることが多いので、少ない準備資金でも創業を応援してくれる制度と考えて頂ければよろしいかと思います。
2.3 制度融資
制度融資は民間の金融機関からの借入を行う時に、信用保証協会に保証料を支払うことで、借入をしやすくする制度です。
民間の金融機関にとっては、新しく創業した人にお金を貸した場合にはお金が返済がされないリスクがあるのので、余程の条件が揃った会社でない限りお金を貸すことは慎重にならざるを得ないのが現実です。
そこで、信用保証協会に創業者が保証料を払うことで、仮に創業者が返済ができなくなった場合には、信用保証協会が民間の金融機関に返済をすることで、民間の金融機関が貸付をしやすくしたものです。
制度融資の場合には、金利が1%台で低金利なる点は魅力的ですが、自己資金の条件が1/2以上であったり他の条件も日本政策金融公庫と比較して厳しくなっています。また、融資の審査に数カ月を要するため創業段階では、まず日本政策金融公庫からの創業融資を受けてから、制度融資を検討するにがお勧めです。
3.補助金
補助金は、借入金と異なり返済不要な資金ですが、補助金の公募内容を確認し申請を要件を満たした上での申請が必要になります。また、申請時に作成した計画の実施報告が必要になるが通常です。
創業者を対象とした補助金としては、「地域創造的起業補助金」がありますが、平成28年度以降の採択率は100件程度で採択率も高くはない状況です(平成27年度までは採択数、採択率も高い補助金でした)。
事業計画の作成を専門家と相談して作成し、創業の準備をする上では有意義なものですが、資金調達のスピードと確実性からいうと、最近の状況では不確実性が高いといわざるを得ないものにいなっています。
4.その他
4.1 ビジネスプランコンテスト
創業者や創業後間もない方を対象としてビジネスプランコンテストに参加することで、資金を調達する方法も考えられます。
ビジネスプランコンテストによっては、入賞者の特典として賞金が与えられるものがあるからです。ビジネスプランコンテストによっては、専門家のアドバイスを受けることができたり、同じ創業を志す仲間との交流の場を設けるようなコンテストもあるので、検討の価値はあるかと思います。
一方で、ビジネスプランコンテストの最終段階までにたどり着くには数カ月の時間を必要としますので、事業に集中する時間が少なくなることや、公開できない企業のノウハウがある場合等には作成するビジネスプランに制約が出てしますうというデメリットもあります。
4.2 クラウドファンディング
創業する予定の事業内容、プロジェクト、製品、サービスを公表して、インターネット上で不特定多数の人から出資を得ることができるクラウドファンディングサービスを活用する方法もあります。
クラウドファンディングでは、プロジェクト内容、提供しようとしている製品、サービス内容に共感を持った人、応援したいと思った人が資金を提供することになるため、やろうとしている事業等の内容の市場の声を確認することができるというメリットがあります。また、融資のように自己資金の準備が不要という点もメリットとして挙げることができます。
ただし、クラウドファンディングの場合には、目標として設定した資金調達の金額を達成できない場合には、資金調達が成立しません。不特定多数の人から共感を得ようとするような目新しい事業や社会的な事業内容の場合に資金が集まり目標が成立しやすい傾向があります。そのため、通常の飲食店や、美容室、サロン等、過去に創業する人ご自身が経験してきた内容をもとに着実に創業をする場合には適しているとはいえません。
4.3 インターネットを使った融資サービス
最近がインターネットを使った融資サービスも増えてきました。別の記事で紹介していますので、こちらをご参照下さい。
5.まとめ
創業段階で資金調達をする方法は複数ありますが、創業のために必要な資金の一部は、自己資金として準備する。その上で、日本政策金融公庫からの融資で必要資金の不足分を補う方法が一番おすすめです。
資金調達のご相談は無料で承っておりおりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。