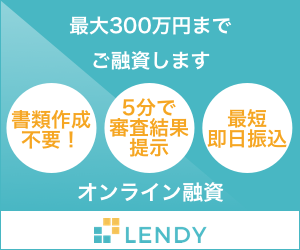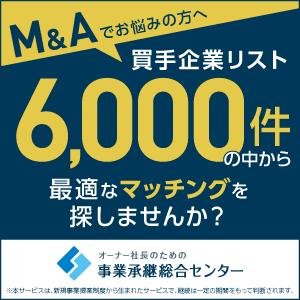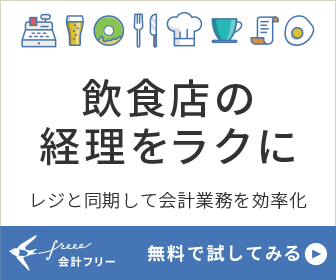創業を決めて会社を設立した後であっても、現実にはすぐに営業が開始される訳ではなく、売上が立つためには一定の準備期間と準備のためにお金がかかる事があると思います。
例えば、会社設立登記後に受注を確保しておくために、創業前から知っている見込客先を回り会社パンフレットやチラシを渡しに行く必要があった。
この場合のパンフレットやチラシの費用や旅費の会計処理はどのようにするのでしょうか?
開業までの費用は、原則として費用として処理できます。そのため、領収書はしっかり保管して顧問税理士に提出しましょう。
また、会計上は、費用として処理するだけでなく繰延資産として5年間で償却することもできます。初年度にまとめて費用にせず2年目以降に繰延ることができるってことです。
税務上は、任意償却が可能です。任意償却では、費用計上する金額を0円から開業費の全額までの範囲で納税者が自由に決めることができます。創業後間もない会社は、税務上の処理に従う事が多いので、こちらが一般的な方法かと思います。
最後に、参考として会計基準(実務対応報告)の規定を一部記載します。
(開業費の会計処理)
開業費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、開業費を繰延資産に計上することができる。この場合には、開業のときから 5 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。なお、「開業のとき」には、その営業の一部を開業したときも含むものとする。また、開業費を販売費及 び一般管理費として処理することができる。開業費とは、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支 払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始時まで に支出した開業準備のための費用をいう。
(会計処理の考え方)
開業費の範囲については、開業までに支出した一切の費用を含むものとする考 え方もあるが、開業準備のために直接支出したとは認められない費用については、その効果が将来にわたって発現することが明確ではないものが含まれている可能性がある。 このため、開業費は、開業準備のために直接支出したものに限ることが適当である。