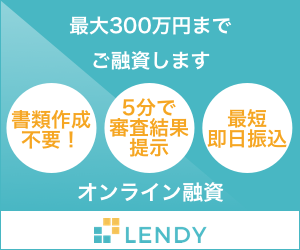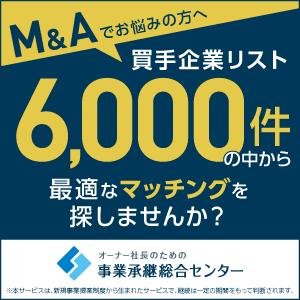目次
1.なぜ納税額の予測と税金の支払いスケジュールを知っておく必要があるのか
会社を設立した後には、いろいろな種類の税金の支払いが必要になります。
それぞれの税金の支払い額を予測すること、税金の支払い時期を把握しておくことは、お金を残しておくことは会社の資金繰りをしていく上で、とても大切ですので整理しておきたいと思います。
2.ケーススタディ
税金の支払い額の予測と税金の支払い時期を考えていないと資金繰りが厳しくなると考えられる事例を考えてみましたのでご参考にして下さい。
2.1 当期売上が伸びており、利益を計上することが予測される場合
「勘定合って銭足らず」という言葉がありますが、損益計算書の売上高が多く計上されており、最終利益を計上できた場合(又は大きい受注が決まっており最終利益が計上されることが予測される場合)でも、必ずしも手元にお金が残るとは限りません。黒字倒産とも言われたりします。
例えば、売上を当期に計上したが、お客さんからお金の回収に時間がかかる場合(お客さんが倒産して支払いできなくなった場合もあてはまります。)には、利益を計上したとしても手元にお金が少ない状況になります。この状況で、会社の利益を基に算定される課税所得から算出される法人税等がある場合には、法人税等の支払期日にお金が不足するという事が考えられます。
このようになるケースとしては、売上の回収が遅れただけではなく、お客さんへ納品するための商品等を先に仕入れて在庫が多く残っている場合や、(在庫が増えた場合には、原価が減少するので損益計算上の利益は増えます。)売上の回収時期よりも業者への支払時期の方が早い場合にも起こります。
上述した内容を、専門的な用語を使ってまとめると、「運転資本の増加」による資金繰りの悪化と表現することができます。なお、運転資本は、以下の公式で算定します。
運転資本=売上債権+棚卸資産-仕入債務
(売上債権は、お客さんから回収できていないお金、棚卸資産はまだ販売していない在庫、仕入債務はまだ業者に支払っていないお金とお考え下さい。)
この運転資本が増加している場合には、利益が計上できたとしても、お金が減る状況にあるため、納税額の予測と支払い時期も踏まえて資金繰りの計画を立てておかないと、資金繰りがさらに厳しくなる可能性がありますす。
2.2 設備投資を行った場合
運転資本の増加の場合だけでなく、当期に大きい設備投資をした場合にも、利益が計上されているのに手元のお金が不足することがあります。
設備投資をした場合には、損益計算書上、設備投資の全額ではなく、投資額の一部が減価償却費として計上されるため、決算書の見かけ上は黒字になることがあります。
しかし、設備投資の資金を余裕をもって備えていた自己資金ではなく、借入によって調達した場合には、借入金の返済により手元の資金が圧迫される可能性があり、この場合にも税金の支払いにより更に資金繰りが厳しくなることを抑えておく必要があります。
2.3 課税事業者になった場合
2.1と2.2は主に法人税に着目した例ですが、2.3と2.4は消費税の事例です。
消費税は、課税期間の「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されることになっています。
この納税義務が免除される事業者のことを免税事業者といいますが、免税事業者になるか否かを判定する「基準期間における課税売上高」とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
ここで、新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。そのため、創業したばかりの会社の場合には通常は消費税がかからないことが多いです。
しかし、新たに設立した法人であっても増資等により資本金が1,000万円以上になった場合には納税義務が免除されません。また、創業3期になり、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合には消費税の納税が必要になります。
免税事業者であった時には意識していなかった消費税の支払いが実際に必要になった場合に、事前に負担額を把握しておかないと資金の準備ができずに資金繰りが厳しくなる可能性があります。そのため、どれ位の消費税の支払いが必要になるかを予測して、支払期限までに資金繰りの計画を立てることは大切です。
2.4 簡易課税から一般課税になった場合
消費税の納付には、簡易課税制度というものがあります。
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に税務署に提出することで、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる制度です。
会社の経費の中には、消費税のかかるものとかからないものがあります。そのため、消費税の計算をする時には、原則として、それぞれの経費の中身を判定していく課税仕入れ等の税額を計算必要があります。しかし、この簡易課税制度を適用した場合には、業種毎に定められた一定の仕入率(みなし仕入率)を適用することができます。
事業の区分と、それぞれのみなし仕入率は、以下をご確認下さい。例えば、サービス業で、人件費の負担が多い事業の場合には、売上にかかる消費税から控除できる消費税が少ないため原則の計算方法の場合には消費税の負担額が多くなる可能性があります。ここで、簡易課税制度を適用していると、売上高にかかる消費税額の50%を控除することがでく消費税の負担額を少なくすることができます。
・第一種事業(卸売業)90%
・第二種事業(小売業)80%
・第三種事業(製造業等)70%
・第四種事業(その他の事業)60%
・第五種事業(サービス業等)50%
・第六種事業(不動産業)40%
しかし、簡易課税制度は、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下に適用することができる制度になりますので、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円を超えた場合には強制的に一般課税(本則課税)が適用されます。
この簡易課税から一般課税に変更されるタイミングにおいても消費税の負担額を予測しておかないと、従来よりも納税の負担が多くなり、資金繰りが厳しくなるため注意が必要です。
3.税金の年間納付スケジュール
最後に3月決算の会社を例に年間の主な税金の納付スケジュールを記載します。
| 月 | 税金の種類 |
| 4月 | 固定資産税(第1期) |
| 5月 | 法人税、住民税、事業税、消費税 |
| 6月 | ー |
| 7月 | 固定資産税(第2期)、1月~6月分の源泉所得税(納期の特例を適用している場合) |
| 8月 | ー |
| 9月 | ー |
| 10月 | ー |
| 11月 | 法人税、住民税、事業税、消費税の中間納付 |
| 12月 | 固定資産税(第3期) |
| 1月 | 固定資産税(第4期)、7月~12月分の源泉所得税(納期の特例を適用している場合) |
| 2月 | ー |
| 3月 | ー |
(注)源泉所得税で納期の特例がない場合には毎月納付。